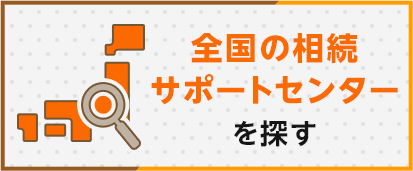はじめに
被相続人が生前に何かしらの収入を得ており、確定申告を行っていたというケースがありますが、確定申告を行っていたこと自体は相続人側で把握はしていたが、手元に申告書の控えがなく、申告内容までは分からないということが稀にあります。
被相続人が確定申告をしていたのであれば、一般的に準確定申告が必要になります。
準確定申告は相続開始後4か月以内に行う確定申告のことで、仮に4か月を過ぎて行うと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される場合があります。したがって相続人は、準確定申告で余計なペナルティを課せられないためにも、被相続人が過去にどのような内容の確定申告を行っていたか把握する必要があります。なお還付の場合はこのようなペナルティはありませんが、還付額を相続財産として計上しなければなりませんので注意が必要です。
「そうはいっても、手元に過去の申告書がないため、内容を把握したくても把握できません」というようになることが想定されます。そこで今回は、このように手元に被相続人の過去の申告書がない場合に、その申告内容を把握できる方法をご紹介いたします。それは「税務署への閲覧請求」です。
閲覧請求について
「閲覧請求」とは、税務署で過去の申告書を閲覧するための手続きです。閲覧した内容はメモしたり、スマートフォンやデジタルカメラなどで画像を保存したりできますが、申告書の控えをもらうことはできません。なお、当該閲覧請求を行えば、請求したその日に税務署で申告書を閲覧することができます。
それでは、請求方法等について解説いたします。
閲覧請求は、申告書を提出した税務署の窓口に「申告書等閲覧申請書」を提出することで行うことができます。その際、今回は被相続人本人ではなく相続人が閲覧請求することになりますので、相続人全員を明らかにする戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図の写し(申請日前30日以内に発行されたもの)、相続人全員の実印を押印した委任状、印鑑登録証明書(申請日前30日以内に発行されたもの)といった書類の提出が合わせて必要となります。なお、運転免許証等の本人確認書類の提出は不要です(戸籍等により被相続人本人と請求人である相続人との関係性が明らかとなるため)。
原則、申請書を提出したその日に税務署内で閲覧することが可能となります。手書きでメモを取るほか、スマートフォンやデジタルカメラを使って静止画を撮影することができます。撮影後は対象書類以外が映り込んでいないか署の担当職員に画像をチェックしてもらい、問題なければ閲覧終了です。
また、過去の申告内容を把握するその他の方法として、「開示請求」(請求すると申告書控えの入手が可能)がありますが、こちらは本人(または代理人)が本人の過去の申告内容を把握するための方法であり、今回のように相続人が被相続人の過去の申告内容を把握する場合に用いることはできませんのでご留意ください。
最後に
手元に被相続人の過去の申告書がない場合であったとしても、上記のような閲覧請求を行えば、被相続人の過去の申告内容を確認することは可能です。ですが、税務署とのやり取りや、委任状の作成に伴う相続人間のやり取りが煩雑になりますので、できれば生前のうちに被相続人とコミュニケーションを取り、申告書の存在や申告内容を把握しておくことが望ましいと考えます。